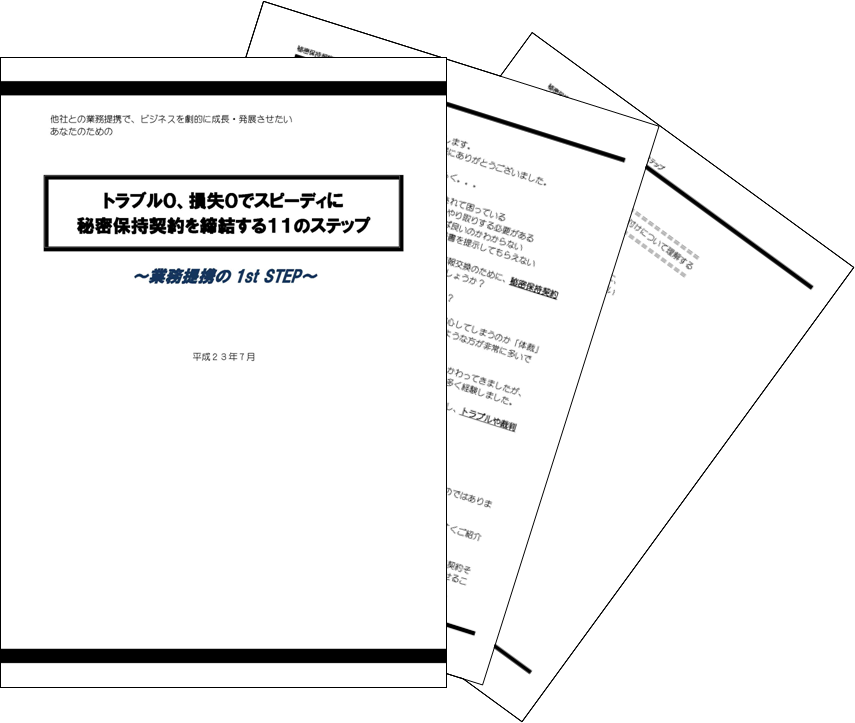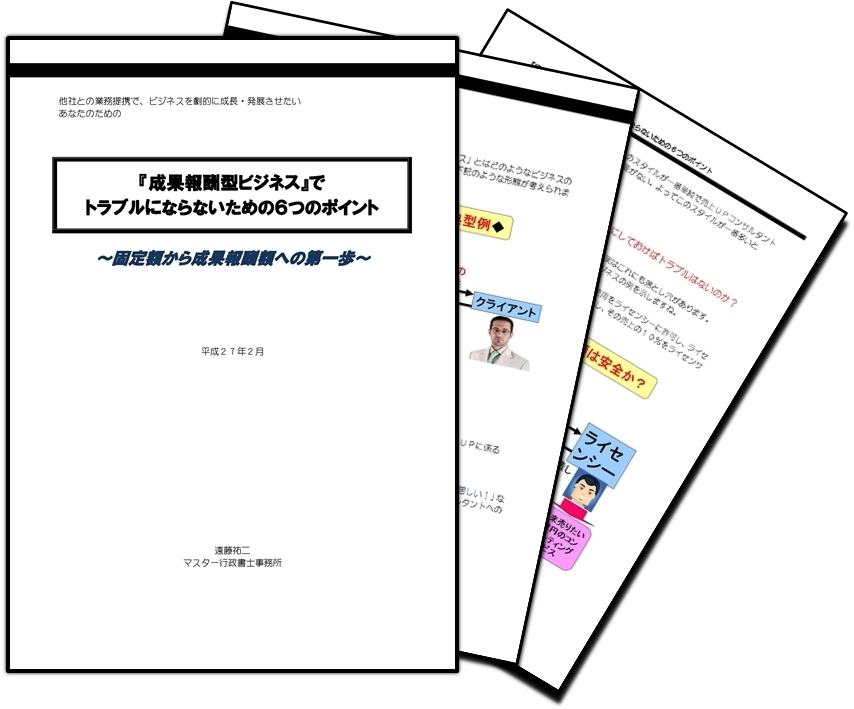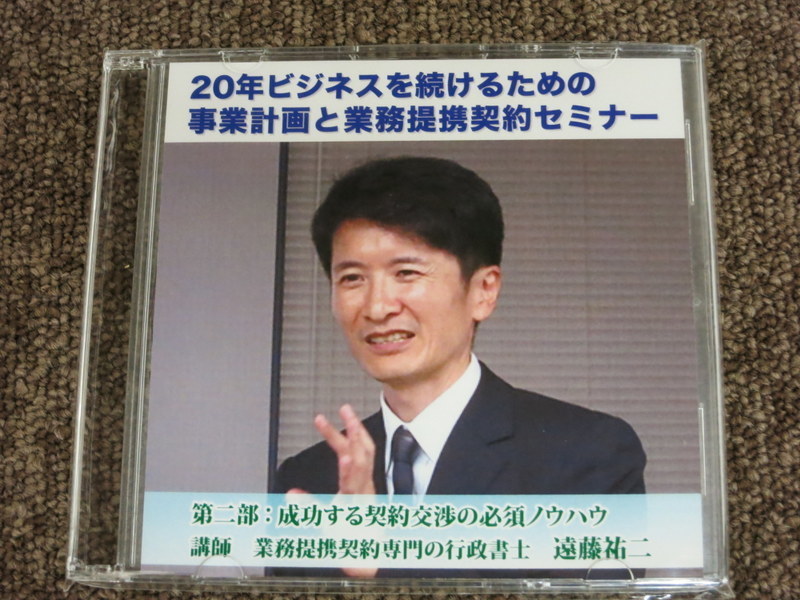契約書と利用規約の使い分け
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
今日は契約書以外の名称の文書のお話をさせてください。
「業務提携契約の専門の行政書士」と名乗っていますが、
たまに「契約書」以外のタイトルの文書も作成します^^
例えば、
・覚書・誓約書・利用規約
などなど。
いずれも、「○○さんに□□をお約束してもらう!」という意味に
おいては契約書と同じですが、その使用する場面が契約書と
違うのです。
ここでは「利用規約」を例にとってお話します。
◆対象は?
・一般的には「個人」の利用者が多いです。
たまに企業もいますがあまり利用規約の条件にグダグダ
言わないような小規模な会社が多いです。
・利用者は不特定多数です。
◆利用規約に同意のうえ利用するサービスは?
・圧倒的に、「Web上のサービス」が多いです。
例えば、「○○自動作成システム」みたいな感じです。
・次に多いのは、「○○会員」みたいな何かの「会員制サービス」
だと思います。
◆書面にハンコを押してもらう?
・あまりハンコを押してもらうことは少なく、ネット上で参照できる
ようにしてあるケースが多いです。
そしてそのサービスの申込ボタンのすぐ横に例えば
「私は利用規約の内容を読み、承諾のうえ本サービスの申し込みをします」
という一文があって、その前にチェックボックスがありそれを
チェックするようにしておきます。
チェックをしないとサービスの申込ボタンをクリックできないように
するのです。
◆記載内容は?
・ほとんど「利用者の義務」しか規定しません。
サービスの運営者の義務についてはほとんど規定していない
いわば一方的な内容です。
上記のような感じで、ぶっちゃけ利用者も利用規約の内容を
いちいち見てからサービスの申込する人などあまりないです。
ところがこのサービスの人気が出て、利用者の中にもある程度、
大きな規模の会社が混じってくるとちょっと困ったことになります^^;
「なんですか?この理不尽かつ一方的な条件は?」
「こんな条件ではこのサービスに申込なんかできませんね。」
「別途覚書で条件変更してくれませんか?」
と利用規約を隅から隅まで読んで交渉を仕掛けてきます。
「サービスの利用者というより業務提携の相手」
というスタンスです。
サービスの運営者としてもたくさんの利用者の中でその会社だけ
条件を変える訳にもいかないので困ってしまう訳です。
よってサービスの提供者として利用規約を使うときは、
==========================
・利用者が不特定多数の一般の個人客または中小企業
・提供するサービス自体もそんなに大きなトラブルに
ならなそうなお気軽な内容のもの
==========================
が良さそうです。
繰り返しになりますが、覚書、誓約書、利用規約などの各文書は
それぞれ根本的な趣旨は同じですがその「使用する場面」が違います。
よってそれぞれの典型的な使用する場面を知っておくと、
あなたのビジネスの幅もグッと広がります。
そんなに難しくないのでぜひ一度、
「自分の場合はどうだろう?」
と研究してみることをお勧めしますよ^^
またメールしますね。
遠藤祐二