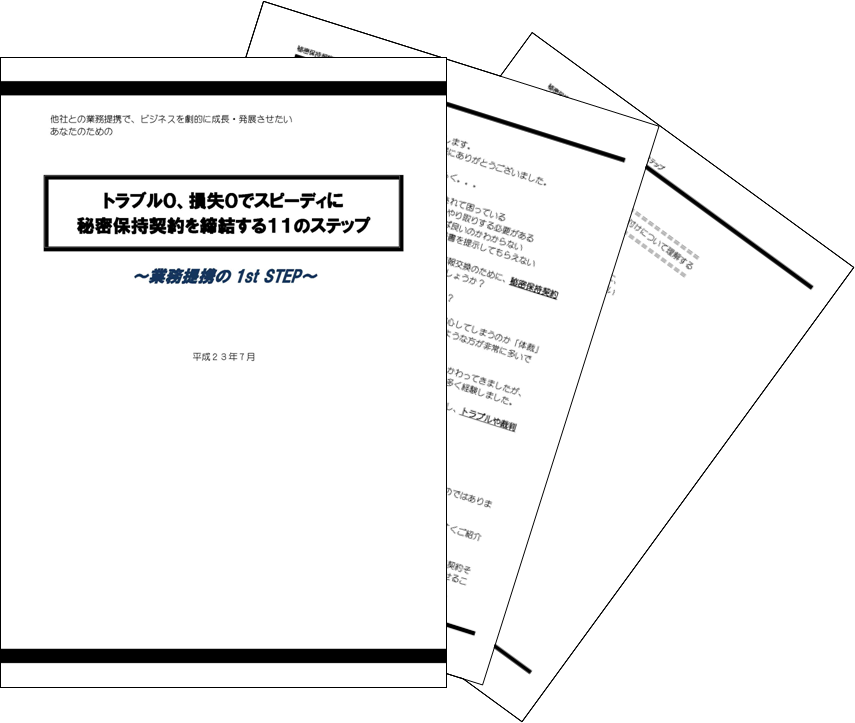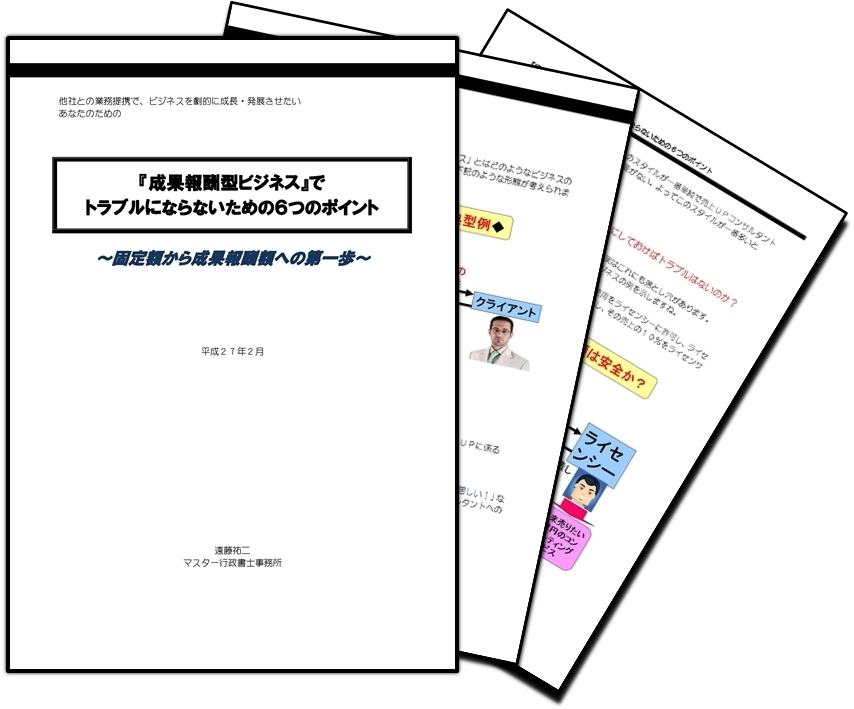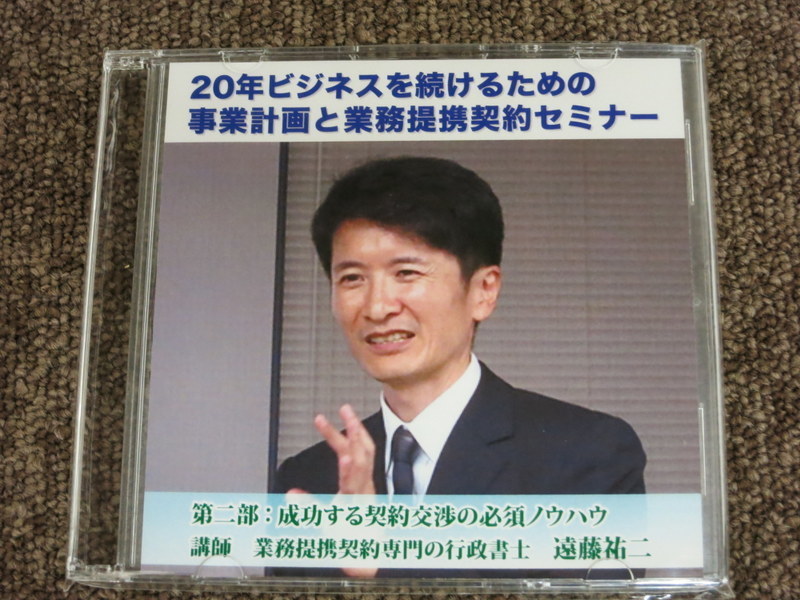以前開催したセミナーの参加者の中に、
ある部品製造メーカーの社長さんがいて、
こんなことを言っていました。
社長:「いやー遠藤さん、今日のセミナーは
本当に勉強になりましたよ!!」
「実はうちはすでに顧問弁護士の先生が
いるんですけど。」
「その先生がほとんど我々のビジネスの話も
聞かずに契約書だけみて、『こんな契約は
ダメだ!リスクが大きすぎる!』と言い切っ
て契約書を修正しちゃうんですよ。」
「私としてはそれはあまりリスクでもないと
思っているのです。」
「でも弁護士先生の言うことには
逆らえずにそれをそのまま客先に出したら
客先が怒り出しちゃって。。。」
「このようなことが本当によくあるんですよねー」
「うちにとってはそれで客先が怒り出してビジネスが
なくなってしまう方が余程リスクなんですけどね。。。^^;」
例えばですよ。
あなたの会社が納める製品の保証期間を、
「10年間にしてくれ!」と書かれている
契約書が相手方から提示されたとします。
そして弁護士の先生がそれを見て、
「10年間なんて保証するのは
リスクが大きすぎる。商法の規定では6ケ月だ。」
と言って契約書を修正するとします。
ところがあなたの会社が、製品の品質には
絶対の自信があり、万が一不具合が起きたときでも、
迅速に問題解決できる体勢がバッチリ整っていたら
どうでしょうか?
長い保証期間を要求されてもそれほどリスク
ではないかもしれないのですよね?
その代わりに製品価格を5割増しにして
くれるのであれば、「喜んで!」となるかも
しれません。
ちなみに商法で一応、「保証期間は6ケ月間」
などと書かれていますが、これは「任意規定」
であり、当事者間の合意でいくらでも変更できる
のです。
あくまでも「当事者間の合意がない場合の拠り所」
として存在するだけです。
だから、当事者間の事情を無視して優先するような
判断はかなり間違っているのです。
業務提携に係る法律の規定はほとんどが
「任意規定」の場合が多いのです。
当事者の合意の方が大事で優先されるのです。
よって、
=====================
「これはリスクです!」と言い切れるのは
法律家ではなくあなた!!
=====================
なのです。
「法律家の言うことだから」と全部丸投げにして
しまってはダメだと言うことですね。
よってあなたも契約交渉に臨む際には
======================
自分で契約交渉については主導権をとって行い、
法律家はあくまでも法律面のサポートに使用する。
======================
ぐらいのスタンスで丁度良いと思いますよ^^
またメールしますね。
遠藤祐二